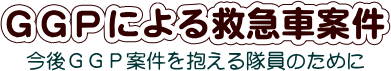|
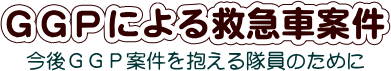
 |
|
|
この救急車案件は2000年年明けの喘息による小学生の死亡から一気に具体化しました。
交通機関の整っていない、道路のインフラ整備も遅れているコスラエ州では救急車は出来得るなら手に入れたい物でした。
しかし、目前に迫るアメリカからの財政援助打ち切りを睨み救急車購入は他の公共事業や州民の大多数が公務員であるため予想される支払い不可能となる人件費圧縮のための早期退職推奨制度による前払い人件費予算などで消えていました。ところがこの幼い命を救えなかったことでこちらへ急遽、救急車が欲しいと正式なオファーが来ました。
今回の案件については州政府が直接、隊員である私にコンタクトを取ってきました。
車両の確保から特装、医療機器の選択など全てを任せられました。このように案件によっては隊員がフルでメインとなり動かざるを得ないケースがあります。
そのためにまずGGP案件を隊員がメインで抱えた場合、以下のことを確認して下さい。
| ★ |
物があってもその自治体と申請国が友好都市関係ではない |
| ★ |
その物を持つ自治体や企業に海外寄贈前例がないため動きが取れない |
| ★ |
ある団体が物を持っていたとしてもいったん、受け皿として自治体若しくは国際事業団への寄贈が必要となるケース |
次に以下の項目を確認して下さい。
| 1. |
自分の出身自治体と派遣要請国との関係が良好である。
他の友好都市と派遣要請国関係が良好である。
出来るなら友好都市であること。 |
|
|
友好都市であれば案件が出てきたとき、自治体へその希望をぶつけることが出来ます。
これは自治体自体でそれに対応する予算を確保していたりしますから非常に高ポイントです。
今回の救急車探しでも残念ながら確保には至りませんでしたが友好都市なら・・・というお話がありました。 |
|
| 2. |
出身自治体が国際協力において関連分野で何らかの実績、前例を持っている。 |
|
|
上記と同様、何らかの援助が必要なとき、実績、前例を持つ自治体はそのスキルがありますから非常に話が早くなります。
救急車に関しては確保された内の1台は実績、前例を持つ自治体でした。非常に対応が早くその指示も適切でした。 |
|
| 3. |
同郷に同職種の協力隊OG、OBがいる。
更に贅沢を言えば派遣要請国からの関係職種の研修員を受け入れている、いた。 |
|
|
これは例えば今回の案件のようにある程度、高額な寄贈では研修員を同国から受け入れている、いた場合、研修員のワークサポートとして援助枠が設けられています。 |
|
|
★更に必要なこととして・・・
| 1. |
日本における協力者、協力機関の確保
今回の案件の場合は同職種はもとより、関連ML、大学、医療機関など
災害救急医療チーム、各消防団などとの連係プレーが必須でした。
これらは医療機器の選定や車両特装など専門分野において非常に重要な情報源であり
協力団体となって下さり無駄なく有効に援助を使うことが出来ます。 |
| 2. |
PC、デジタルカメラ等
今は殆どの国でインターネットが使用できます。今回の場合は基本的なインフラの
状況や医療機器のプラグ、バルブなどの形状を確実に日本へ情報提供するために
欠かせない物となりました。 |
さて、上記をふまえGGPについて話を進めます。
|
| ★まず草の根無償援助プロジェクトとは |
Grant Assistance for Grassroots Project略してGGPと言われています。
このプロジェクトはNGO団体、途上国政府当局に対し実施される無償の途上国開発プロジェクトの支援です。
このGGPには比較的支援金額の小さなプロジェクトに対してはSmall Scale Grant
Assistance略してSSGAやリサイクル・・・例えば今回の救急車など・・・によるリサイクルGGPなどが用意されています。
この日本政府による援助プロジェクトは途上国におけるNGOs、病院、学校、各調査研究、そして非営利組織等への彼等の開発プロジェクトに必要とされる物品や施設など現物支援の形をとるプロジェクトです。
非営利組織、団体であればそれらの国籍を問わず申請可能です。
次にGGPのプロジェクト支援範囲ですが主に
| 1. |
初等教育エリア
例えば施設の一新、学習機器の購入、ハンディキャップ自立支援 |
| 2. |
プライマリーヘルス・エリア
例えば病院の増改築、医療機器の購入、そして救急車の購入 |
| 3. |
Poverty relief貧困改善エリア |
| 4. |
公衆衛生エリア |
| 5. |
環境エリア |
| 6. |
女性の人権等に関する
女性自立、教育、開発活動支援エリア
例えば識字教育、技術移転、自活支援プロジェクト |
となっています。
GGPに関してはその当該国における必要性が高いものから優先的に取り上げられていきます。
この優先順位決定は当該国やそのエリアを管轄している日本大使館若しくは日本領事館が判断することになります。
GGPにおける一般的な支援上限額は$100,000.で幾つかの特殊なケースでも$200,000.までとされています。 |
★ここで内輪話ではありますが・・・・
各大使館や領事館により当年度GGP予算が違うそうです。ここミクロネシアの場合、今年度は1500万円。
ですから申請金額は出来るだけ当該国日本大使館、領事館の予算額を調べ当該国が他にもGGP申請が挙がりそうな地域であればある程度の調整が必要となります。
申請が通過しそうな金額にする、というのがポイントになります。しかも申請時期としては年度末か年度始めが狙い目です。年度末の場合は2月までに年度始めなら4月中に申請をあげましょう。予算確保がしやすいそうです。これらの支援金は当然ですが給与、燃料、移動費、組織の運営経費などには使用できません。
|
ここまでを今回の救急車案件で説明しますと
まず当州政府から医療エリアにおいて緊急時対応の遅れが言われて久しかったこと、今年初めにその不備により尊い幼い命を失ったことなどから協力隊員である私へ救急車購入について相談が持ちかけられました。この案件の目的は医療エリアにおける緊急時対応の充実となりGGP申請条件である非営利目的です。
申請団体も政府組織ですから条件はクリアとなります。
その申請団体のバックアップ団体として個人的に所属しているNGOsを列記してありますがこれらもまた非営利団体ですので問題なくクリアです。
支援エリアはプライオリティーの高いヘルスエリア。
申請金額は車両代金、車両特装費、設備医療機器代金、国内輸送費、国外輸送費などを含めて約$40、000.。
申請時期は4月。新年度予算を真っ先に・・・。
|
|
さて、ここまでが申請準備です。
救急車案件について申請準備期間には
車両の手配
|
・・・ |
日本における協力団体から沢山のご厚意と情報をいただきました。
|
車両確保後は協力団体や情報提供者も確保
|
・・・ |
トヨタをはじめとする各種団体、救急医療チーム、消防関係。 |
| 装備関係の打ち合わせ |
・・・ |
そして例えば車両の場合はミクロネシアは問題ありませんがアフリカのある地域などは左ハンドルしか搬入させない、救急車の場合はサイレンやライトの仕様基準がありそれらをクリアしなければ無駄に終わってしまうケースもありますから事前の当該国調査は必須です。
|
|
|
実際にミクロネシアのケースとしてはお隣ポンペイ州に日本のNGOsから消防車が搬入されましたがホースの形状が違い使用できませんでした。
例えば救急車で言えば車載ボンベなどにこういった問題が起きます。
電気機器を積む場合はプラグ形状、電圧など。
機器に関しては更にメンテナンスなどプロジェクト開始後のフォローアップも含め検討します。 今回は故障しても修理可能なシンプルな機器を同種類で予備の分含め数個ずつ申請。
車両は他にも道路環境、保管状態などによりショックや塗装など装備が変わってきますのでその辺りの現地の事情を必ず調査します。
・・・何にせよ、これは専門家の方々の意見を重視し大丈夫かな・・・と救急関係素人の私は簡単に考えがちなことも沢山指摘を受け申請に向けて準備をしました。申請内容に関し専門の方のバックアップは非常に大切でした。
そして勿論、肝心のプロジェクト内容の検討を政府関係者と頻回、実施しました。
申請を出している政府によっては非常に申請書などの書き方、提出日などアバウトに考えがちですので必ず期日の厳守を促し数字などの複数回のチェックは欠かさないようにして下さい。
|
|
★申請内容は多岐に渡り詳細な記入が必要とされています。
申請書は特に注意することもありませんが申請通過を早くするためにはそのプロジェクト開始時期を新年度の早い時期に設定する、数字の間違いがないこと、案件の緊急性に触れていることなど、もうこの案件のきっかけとなったようなケースを繰り返さないためにも細心?の注意を払い申請書は政府と相談を重ね書きました。
|
★申請書が出来上がったら大使館へ提出。
今回の救急車案件は事前にミクロネシア日本大使館書記官鳥海氏と調整を重ねながらの申請でしたから非常に申請書類の提出から決定まで短期間でした。
申請前段階においても鳥海氏、JICA/JOCV ミクロネシア事務所の三国調整員のお二方が確実なサポートをして下さいました。
|
★申請書を受け取ると大使館はその申請書を検討し現地調査にいらっしゃいます。
そしてオーケーならば後日、申請組織と大使館との正式調印が行われます。
|
★そしてプロジェクトは始動します。
救急車案件において問題となったのが支払方法。原則として大使館は日本へは支払いません。
途上国支援ですから主体となっている途上国組織、当該国へ小切手で申請通過金額を一括支払います。
それは申請通過、調印後約2〜3週間以内に実施されます。
しかし・・・残念なことに・・・・たまにですがその支払われた援助金が消えてしまいます。そうしますと今回の救急車の場合、既に車両をトヨタに搬入し装備し医療器械を購入、船に乗せてもその代金は徴収できないのです。
で、裏技として使用したのが代行。
途上国の現状を誰よりも把握している大使館ですから代行という手段を持っています。代行の手続きは当該国から管轄大使館へ支払い委任状を書いていただければそれでオーケーです。大使館は支払いを代行し日本なり支払先へ送金して下さいます。但し、送金手数料は当該国持ちです。
|
★案件物件が到着したら
残念ながら私はこの案件の当地到着を待たずに帰国するため、肝心の詰めが甘くなり不本意な結果となりますがここで最終的なチェックが必要になります。
備品の個数、形状、使用可か否か・・・など細部に渡り確認が必要となります。
不備があった場合は各関係団体と連絡を取り適切なフォローアップを実施することになります。
|
★最後に・・・
GGPは湯水のように湧いて出る物ではありません。
申請を打診されたとしてもしっかりと状況を判断し有効な申請であるかどうかを判断しなければなりません。
どうぞ適切かつ有効な申請を目指して下さい。
|
★今回の案件への協力団体
・東京大学国際保健計画 坂野晶司 先生はじめ国際保健ML
・愛媛大学救急医療部 越智元郎先生はじめ救急医療ML
・トヨタ・テクノクラフト
・山形トヨタ
・赤十字山形ブランチ
・ワコー商事
|
| ★救急車の到着★ |
救急車の到着を待たずに帰国してしまった私・・・。
現職参加という制度での派遣では任期の延長が認められませんでした。
泣く泣く看護婦隊員の河田さんに引継を頼みました。
現地を走る日本の善意の形をひとめ自分の目で見たかったのですが・・・・。
さて・・・・以下は河田隊員からの報告です。
|
救急車ですが、予定通り8月7日にコスラエ港到着
|
 |
翌日の8日に病院に引き取り、1週間後の15日にセレモニーが執り行われました。
州立病院長ドクター・Hirosi氏が入れ違いで出張のためポンペイに行ってしまいましたが、州政府が取りしきり、病院で(オフィスと病棟をつなぐ通路で)セレモニーが行なわれました。
病院事務長ミスター・Arthyは「10分ぐらいのもの。」と言ってましたが、パスタ−のAlu(お祈り)から始まり、ガバナー(州知事)のスピーチ、大使のスピーチ、鍵の引渡し、テープカットと、20分くらいの内容でした。
   |
救急車内の設備についてですが、頂いていたリストを元にチェックしていきました。美智子さんが心配されていた酸素ボンベですが、救急車に取り付けられているのは病棟などで使われる小型のボンベよりもやや小さめのもの2つで、当初調べていた型ですが、はっきりわかりません。ただ、ドクターに見てもらったところ、充填できるということです。
EKGモニターなどの個数に異常はありませんでした。
ただ1つ、アナログ時計が入港当時から見当たらず、内尾さんにお尋ねして出港前の内装写真を送ってもらったのですが、やはりどこにも見当たらず、どこかで盗まれたのではないか・・・、という話になりました。どう対処して良いものかもわからず、病院には今のところ言っていません。
私が気がかりな今後の運営のことですが(気になってしまいます、どうしても)、担当者は一応救急担当の男性のナースという事になっています。でもドクターさえもよく知らない人がいて有効に活用されるのか、適正に使用されるのかは心配ですね。
コスラエ港での様子と、セレモニーの様子を撮った画像をお送りします。 |
|
さて・・・
ここまでの注意点と問題点。 |
|
途上国への機材の搬入スケジュールはかなり、本当にかなりの余裕を持ってでなければいけません。下手をすると受け取り責任者がいない・・・と言うことになります。
しかも政府間でのやり取りなので引き渡し式など正式な文書を交わし、受け渡す場を設けなければなりません。そのスケジュール管理も気をつけなければなりません。
次に搬入機材の物品確認です。
今回も無くなっていたものがありましたが事実を言えばこの程度の盗難でホッとしていると言うところです。盗難は確実に起こると言っても過言ではありません。ともすれば、そのもの自体が消えると言うこともあります。
そして機材の使用チェック・・・確認に確認を重ねたにもかかわらずやはり、仕様が違うなど、問題点が出てきます。現状を確認しながらでもこういったことが起こり得ますので機材の詳細、仕様はしつこいぐらいの慎重さでチェックしなければなりません。
機材の点検、式典を終えるとその後は適切な使用がされているかが一番の問題点となります。
車などの移動手段となり得る物品では途上国では移動手段が限られているため時には政府高官の私用車と化すケースもあります。当時の要請内容と違う使い方をされてしまい充分に機能することが出来なくなる場合が多いのもこうした援助の影の現実です。ですからフォローアップは必要です。
これは今回の場合、日本の皆さんの善意と税金が使われ救急車の必要性を訴える現地のニーズを考えると厳しくても口うるさくてもチェックし続けなければなりません。 |
|
| ★では・・・・その後・・・・★ |
その後ですが、そんなに頻繁に重症なケースがあるわけではありませんが、軽度の喘息発作、高校生が授業中に失神(軽いテンカン発作と思われる)、など使用されています。
機材に関してですが、車内に取りつけてある2本の小さい方の酸素ボンベですが、コスラエで充填できない事がわかり、薬局を通しポンペイに問い合わせてなんとかなる、という状況だそうです。残りの1本を現在使用中と言うことです。
パルスオキシメーター、ポータブルのEKGモニターは救急車だけでなく、病棟でも活躍しているそうです。携帯吸引機も有効活用されているようです。酸素ボンベが少し心配ですが、それなりに努力をしているようです。
いっぱいあった小さなぬいぐるみはあっという間になくなり、(スタッフが持ち帰った可能性が高い)
あと、救急車にはってある"かわいい犬とハート"のステッカーの予備が貼られた車が走っているのを先日見付け、後を付けて見ると、なんと救急車担当者の当人が「キャトー」ということで使っておりました・・・。
|
|
以上が昨年の秋までの状況です。
太字にしました犬のステッカーは救急車の手配、特装など一手に引き受けて下さった横浜にありますトヨタテクノクラフト社の女性スタッフさんが今回の援助のために作って下さいました。
キャトーというのは現地語で可愛い、素敵・・という意味です。
 |
 |